 |
 |
■1.卵や雛を守る親鳥
|
 |
 |
| コチドリの擬傷 |
土手の上で警戒するコチドリ |
2.コチドリの擬傷
「ピョーイ」と鳴きながら飛び立つと、チドリ特有の美しい輪郭の翼形を見せる。
長い足を目にも止まらぬ速さで動かして走るのを見ると、「チドリ足」なんていう言葉は、一体誰がこの鳥のどこをみていいだしたか、不思議な気がする。
スズメとヒヨドリの中間ほどの大きさで、背面は褐色がかった灰色の目立たない色彩の鳥である。
池だけでなく、川原や田にも現われる。大部分が夏鳥だが、冬に少し見られる年もある。イカルチドリは、コチドリよりも少し大きく、シロチドリは海辺を好む。
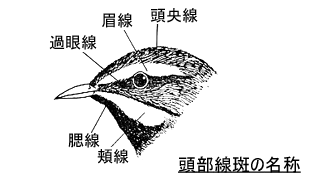 チドリの仲間は、川原や海辺の草のまばらな砂礫地に巣を作って卵を産む。巣は小さなくぼみを掘り、中に小石や貝がら、木片を少し敷いただけの簡単なものである。そんな巣でも、卵の保護色はすばらしい。うっかり歩くとふみつぶすまで気がつかないほど巧妙な色どりである。 チドリの仲間は、川原や海辺の草のまばらな砂礫地に巣を作って卵を産む。巣は小さなくぼみを掘り、中に小石や貝がら、木片を少し敷いただけの簡単なものである。そんな巣でも、卵の保護色はすばらしい。うっかり歩くとふみつぶすまで気がつかないほど巧妙な色どりである。
しかし、この保護色も野獣やヘビ、カラスには、それほど威力はないらしい。被害にあう巣が、あまりにも多いことが、それを裏付ける。
孵化した雛は、すぐ巣を離れ、親鳥の後を追って水辺へ移動するが、ここでも飛べるようになるまでに、多くの敵から狙われる運命にある。
チドリの雛は、ヒヨコを小さくした姿を思い出していただければ大きな違いはない。親鳥が、敵の接近を知らせる警戒の叫びをあげると、雛はその場に伏せて硬直状態になる。ときには指で触れても動かないほどの徹底ぶりである。へたに動くとかえって危ないことを先天的に知っているのである。一方、この危険の多い場所に巣を作らねばならないチドリの親鳥の神経は過敏すぎるといってもいいすぎでない。
私たちが、いまその雛や卵に近づいたとしよう。親鳥は我々が気付かないほどの距離から巣を離れ、目立たないように低い姿勢でしばらく走ったあと飛び立つ。そのときはじめて警戒の声を上げる。巣のある方向を感づかれないように、私たちを違う方向へ誘導しようとしているのである。
それにもかまわずなお巣に近づけば、かえって警戒を止め、姿を消してしまうことが多い。騒げばかえって侵入者に巣の存在を教える結果もあることを知っているからである。卵や雛の保護色を信頼し、運を天にまかせるといったところだろう。
ところが、ときには擬傷という思いきった手段をとることがある。擬傷というのは、自分が傷ついてもがき苦しんでいるようすを演じ、敵の注意を自分に引きつけさせて、卵や雛と反対の方向へ敵を導こうとする必死の演技である。
敵が獣や子供であれば、うまくだまされて傷ついた親鳥を捕えようと追うであろう。
目的を果した親鳥は、ある地点まで敵を誘導すると、ふつうの姿勢にもどり、さっと飛び去る。だまされたと気がついた時には巣よりだいぶん遠くまで引っばってこられていることになる。
擬傷はそんなに頻繁に使う手でない。コチドリの巣はこれまで多数見ているが、積極的な擬傷に出くわしたのはたった一回きりである。擬傷は孵化に間近い巣や、雨の強い日によく行なうという。卵や雛がぬれるとその生存に危険があり、一刻も早くその場を立ち去ってもらわなければ困るような時である。
6月の小雨の肌寒い日であった。半分干上った池の岸を右に土手、左に水際を見ながら北向きに歩いていた私の目の前3mほどの所に一羽のコチドリが舞い下りた。警戒心の強いコチドリが、わざわざ人の前へ飛んで来るのだから驚きである。そして、くるりと向きを変えてこちらに背を向け、ばたばたやりだした。「ヂュ…」というような怒りの声をあげ、中腰ほどの高さに身を保ちながら、左翼を大きく広げ、右翼はそれよりやや小さ目に広げ、銃傷を負って飛べない鳥のようすである。尾は扇のように広げてふるわせている。脚は見えないが、体の高さから想像すると、半分折り曲げた程度らしい。頭は前に垂れているようである。そして、わずかながら前へ前へと進む。はじめてみる本格的な擬傷である。
私は鳥の導きにしたがって、ゆっくりと前進した。鳥は一定の距離を保ちながら、前へ進む、小走りに近づいてみた。一瞬、親鳥は、ぱっと飛び立って数メートル先に下り、こちらを向いて立っている。全く人を食った態度である。そして、もう追わないと見ると、先ほどと同じぐらいの所まで走って戻ってきて、またやりだした。二度、三度、くり返したが同じである。
今度は、大きく一歩後退してみた。ただちに擬傷を止めこちらを向いてつっ立っている。擬傷しながらの後退は姿勢から見て無理らしい。2〜3秒、私の顔色をうかがっていたが、ちょこちょこと走って、前と同じ距離まで戻ってきて擬傷をくり返しはじめた。もう一度やってみたが同じである。
ためしに、私を誘おうとする反対の方向に10mほど進んでみた。気も狂わんばかりの擬傷を期待したのである。予想は見事にはずれた。擬傷を止めてしまったのである。そして10mほど離れた位置に立ち、心配そうにこちらを向いて、例の頭をぴょこんと下げる動作をくり返しているだけである。このままだと卵や雛を探すにはだいぶん時間がかかりそうである。できるだけ多くの動作も観察したい。しかし、これ以上時間をかけることは、雛や卵を危険な状態にさらすことにもなるので、ここは一応引き上げることにした。そして、いったんその場を去り、30分ほど後、今度は親鳥に気づかれないように、ここと思う場所に急襲をかけることにした。まず、土手の下をまわって、藪かげからようすを調べた。もし、親鳥が、私に気づいて走り出したとしても、先にこちらが、そのスタート地点を知れば、探すときの大きな手がかりを得たことになる。
雛はすぐに見つかった。孵化して2日ほどと推定できる小さな雛が、水際の小石にはさまれるように伏せていた。今度は、擬傷はやらなかった。10mほど離れて見守っているだけである。私はそれだけ見て早々とその場を去った。コチドリの通常の産卵数は4個であるのに、雛は一羽だけであった。他の雛は離れて伏せているのか、まだ孵っていないのか、そこまで見るだけの心の余裕はなかった。早く親鳥に雛をかえしてやりたかったからである。今、思うと少し残念だが、あの時はあれでよかったと自分にいいきかせている。
警戒にあたる親鳥は常に1羽であった。そのつれあいはどこで何をしているのか、ついに姿を見せなかった。近くに幾つかのコチドリがいるので、そのうちの1羽が、それだろうと思われる。動作にあらわさないにしても心配して見守っていたはずである。
話は変るが、カルガモでもこれに似た動作を見た。加古川の河川敷の水たまりを遊泳中の6羽以上の雛をつれた親鳥にばったり出会ったときである。水上であったので、頭で水をすくって体にかける水浴のような動作を見せながら、翼が傷ついているように見せかけた。雛はいち早くアシの茂みに入って見えなくなった。巣立ち雛を持つホオジロもこれに似た動作を見せることがある。
|
コチドリ チドリ目 チドリ科
雄雌同色、額は白色、頭上に幅広い黒色の帯があり、眼の後方までつづく黒色の太い過眼線がのびる。まぶたは黄色、上胸には後頸までのびる幅広い黒い線があり頸輪をつくる。体の上面は灰褐色、下面は白色、尾は最外線の2対は白色で、他は暗褐色である。嘴は黒く、 は黄色、虹彩は暗褐色である。幼鳥や成鳥の冬羽では過眼線や頸輪などの斑紋が不明瞭である。 は黄色、虹彩は暗褐色である。幼鳥や成鳥の冬羽では過眼線や頸輪などの斑紋が不明瞭である。
嘴峰 12-14mm、翼の長さ 110-120mm、尾の長さ 50-60mm、 23-25mm、開長平均 351mm、全長平均 169mm、体重平均 39g。 23-25mm、開長平均 351mm、全長平均 169mm、体重平均 39g。
北海道、本州、四国、九州、対馬、佐渡などで繁殖するが、冬はアジア南部からインド、スリランカ、アフリカまで渡る。国外ではヨーロッパからアジアにかけて広く分布し、冬はそれらの南部へ移動する。 |
英語名 Little Ringed Plover
学 名 Charadrius dubius Scopoli
|
|