 |
 |
 |
4.照葉樹(常緑広葉樹)林時代
|
大阪湾沿岸の海岸平野をはじめ、六甲山地にいたるまで、6,000年前から5,000年前にかけての1,000年間に、現在の森林の原型は完成されたとみてよい。
神戸では、海ぞいの低地から六甲山の400メートルぐらいまではアラカシ、ウバメガシ、シイ、ヤブツバキ、ヤブニッケイ、カナメモチなどの樹木が生え、さきに述べた森林帯がほぼできあがっていた。それでは5,000年以降にどんな変化が森林社会に起こっただろうか。まず4,500年前から4,000年前ごろにかけて小さい寒冷気候が訪れたのか、モミ、ツガ、コウヤマキ、スギなどのいわゆるモミ・ツガ林とか中間温帯林といわれる樹種群が一時的に増加する。現在のモミ・ツガ林は500〜600メートルに自生するが、この時期にその森林帯が形成されていたかどうかは、明らかでないものの、花粉化石の出現率が高くなる。このモミの出現傾向については、次のような興味あることがわかった。
|
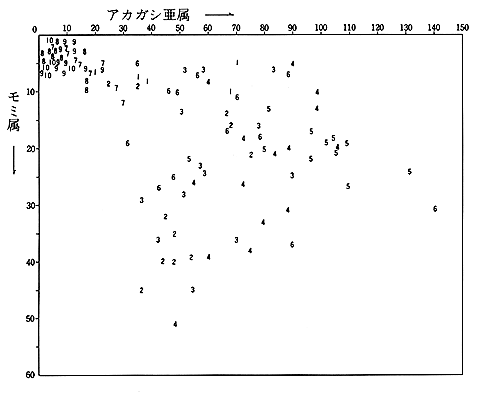
モミとカシ類(アカガシ亜属)との相関図 (Maeda.Y., 1977) |
まず、モミと正の相関にある樹種群であるが、コウヤマキとツガがピタリといっていいぐらい増減の時期が一致している。モミ、とコウヤマキの相関図をみると、両者は正の相関で、ともに同じ森林社会を構成していたといえる。そしてツガもこれに伴う傾向を示す。モミ・ツガ林は完新世の7,000年前ごろから、すでにその樹種構成の基本型はできていた。
ところが、モミとカシ類との相関をみると、相関図では一見、無相関のように見える。けれども年代を追って検討していけば、7,000年前から5,000年前にかけての時期はともに増加し、両者は正の相関である。しかし、4,000年前から2,000年前にかけては負の相関に変化している。これに対するひとつの解釈に、モミ林もカシ林もともに5,000年前までは増加するが、4,000年代になるとカシ林の上限近くにモミ林が位置するようになったのではないか。そして、小寒冷気候が訪れるたびにモミ林がいくらか降下してくるために花粉化石の出現率が相対的に増加してくる、という予測がなりたつ。しかし、これはあくまで予測の域を出ず、今後さらにいろいろな地域での花粉分析がなされたならば、解決できる問題である。
このようなモミ、コウヤマキ、ツガ、それにスギを加えた樹種群が一時的に増加するのは、3,000年前、2,000年前にも起こっている。ただ、玉津環境センターでは、ツガの花粉は8,000年前以降、ほとんど産出しない。これは明石川流域にはツガの生育地にみられる土壌の少ない、やせ尾根のような場所が少ないことによるものと思われる。
また、2,000年前ごろからマツが急増する。大阪湾沿岸では、私が花粉分析を行なった地点で2,000年以降の堆積物があったのは神崎川口の中島大橋だけであるが、ここではマツが急増する時期はみとめられなかった。しかし、河内平野古市で行なった安田さんの報告にも、古谷さんの分析結果にもこの時期のマツの急増が重要な植生変遷の問題として指摘されている。
このマツ急増期は弥生時代の前期にあたり、ようやく古代人の農業生産が低地に定着する水稲栽培を本格的に行なうようになり、海岸低地や川ぞいの低地を切り開いた結果、二次林であるマツの花粉が増えたものだと、はやくから注目されていた現象である。人間の生産活動の活発化にともなって生活空間が拡大されて、その結果、二次林の増加がマツ林の増大をよんだとする説である。
|
|
|